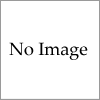
好奇心からの行動が親友を作り出し、何もできないままその親友を失ってしまう。その口からはもう言葉が出てこないけれど、心には大切なものが刻み込まれていると信じている。生涯を通じても出会うことのできない人に、ほんの短い時間でも一緒に過ごすことができたことが、大きな意味を持っている。

ロバート・デ・ニーロとロビン・ウィリアムス主演の同名映画の原作ですが、何回も改訂されているので、原作であると同時に撮影の後日談も載っている面白い本です。

30年も昏睡状態の難病の患者(ロバートデニーロ)に、医師セイヤー(ロビンウイリアムズ)が新薬を投与。奇跡的に目覚め、普通の人間たちが当たり前に持つ「人間関係」を持てるまでになる。
二 人とも「ストレートな言葉」ではなく、あえて「表情としぐさ」でものを語っていると言ってよい。患者として、医師として、それぞれの立場で自分の限界を知 りつつ、それぞれが日々を精一杯すごす。残酷な「限界」。「その日」を迎える二人の気持ちを思い、見る者は胸を締め付けられ、涙する。いっそ生きる喜びな ど知らずにいたほうが良かったのでは、いや、知ってよかったのだなどと、自問自答を繰り返す。胸を打つヒューマンドラマ。忘れられない感動が残ります。
なんと言っても名優ロバートデニーロとロビンウイリアムズだったからこそ、これだけの感動を呼び起こしたのだと思います。

映画のレナードの朝が好きで購入。
映画では沢山の患者が写っていたが、各自に対する細かい描写はなかった。しかし、本では患者一人ひとりについて「入院に至るまでの経緯」「入院中の生活」「特徴」「L-dopa(エルドーパ)投与までの流れと決意」「観察日記」などが細かく綴られている。 映画ではドラマチックに描かれていた部分もあったのではないかと思うが本はほとんど報告のような形をとっている。 これを読むと、患者それぞれの症状は違うことや薬の投与量が違うこともよくわかる。しかし、その分すこし分厚目の本になっていて、1日で読むのは厳しいかも。読みごたえはあります。

ペニー・マーシャル監督の映画はハートフルで好きなものが多かった。
後年、数作が興行的に失敗続きだったせいか、新作が途絶えてしまったのが残念。
マーシャル監督の特徴は主要人物を描くだけでなく、
周囲の人物にも小さいながらエッセンスの効いた役どころを演出していること。
それは「プリティ・リーグ」で、およそ泣くことに縁のないようなスラッガーが涙を見せたりと、
観客の心情がこういう第三者の心情であることをわかって演出しているから。
日本映画のように泣いている人物だけをクローズアップで見せるのではなく、
周囲にいる人物の心情が見ている観客の心情であることをわかっているのだね。
リアクションの大切さをわかって演出することも大事だし、さりげなく演じてみせる俳優の力量もある。
有名であろうが無名であろうが、ひとつの作品を作り上げる上で何よりも大切なこと。
「レナードの朝」も主題はともかく、
ロビン・ウィリアムス演じる医師と、その助手を演じた看護師のちょっとしたエピソードに救われている。
人は目の前にある幸せに気がつかないもの。
それは当たり前に好意を寄せた女性とのダンスであったり、コーヒーに誘われることだったりする。
ダニエル・キースの「アルジャーノンに花束を」を思わせる内容で、
ロバート・デ・ニーロの熱演も見事であるが、
周囲に配置された小さな役の俳優たちのさりげない演技も見応えがある。
日本には「ファンは俺のアップが見てえんだよ」と宣う役者もいるが、
映画ってそんなものじゃないんだよと、教えてあげたい作品。
|