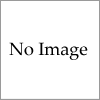
1991年発売
当時は20000円したそうだ
コンパイラーはドイツ人
ああ、欲しい
、、、もってへんのかい

私もアリソンと同じように死者が見えるので、自分の事のようです・・・また、話していると相手が考えている事も分かってしまうので、職場では、苦労しています。とても参考になりますね!

※ラストに触れているので、未見の方はご注意を
単なる復讐劇かと思いきや、これは侮れない映画だ。
まず、全編を覆う死の雰囲気に驚かされる。主人公が巻き込まれる陰謀、フィクサーの抱える病気、そして放射性物質と、登場人物全員が、死に向かって確実に歩みを進めている。 逆に浮かび上がってくるのが、劇中を(少なくとも画面上は)生き残る人物たち、すなわち、殺された娘の友人の女性、主人公の同僚の刑事、そしてラストの警官の3名だ。
彼らはいずれもこう言う。「俺(私)には子供がいる」 ここから作品のもう一つの側面が見えてくる。それは、死ぬ事が運命づけられている人間にとって、我が子の存在こそ生きる意味たりえる、という価値観だ。そして、おそらくそれは(観客が受け入れるかどうかは別として)キリスト教的な価値観ではないかと思われる。
娘が撃たれる場面を見てほしい。血まみれの娘を抱きかかえる主人公の首から垂れ下がるネックレスには十字架が彫られており、さらに彼は娘に「神よ、あなたの愛と慈悲によって…」と、臨終の祈りを口にしながら泣き崩れる。彼はクリスチャンなのだ。(ちなみにメル・ギブソン自身もカトリックの信者だ)
原題を訳せば「暗闇の淵」といったところだろうか。オリジナルのTVシリーズと同じ題名だが、本作における「暗闇」とは、我が子を失った主人公の、現実に対する絶望である。彼は現実を生きながら、既に魂は死んでいる。だからこそ、ラストで我が子によって暗闇に「光」がもたらされる。この作品は、魂の救済の物語でもあるのだ。
マーティン・キャンベルの歯切れの良い職人的な演出は、時としてこの作品が持つもう一つの側面を見えにくくしがちだが、久々に薄っぺらではない、映画を読み解く楽しさを味わわせてくれる作品である。
| 
