
嘘つきアーニャの真っ赤な真実 (角川文庫)
ロシア語の通訳として名を馳せ、その後手練のエッセイストとして評価の高かった米原さんは、 
不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か (新潮文庫)
故米原女史は言うまでもなくロシア語通訳の第1人者であったが、同時にエッセイ家としても有名であった。しかも、印象とは異なり下ネタをふんだんに交え、自身の通訳経験を踏まえながら、ユーモアの中に国の相違による価値観の違い、相互理解の難しさをサラリと語って読者を楽しく啓発してくれた。本書の題名は同時通訳にあたって「意訳ではあるが相手の顔を立てる訳を選ぶか、原文に忠実ではあるが相手には真意が伝わりずらい訳を選ぶか」という通訳者の究極の選択を意味している。 
オリガ・モリソヴナの反語法 (集英社文庫)
米原万里さんの唯一の長編小説である。米原さんが書くものはほとんどがエッセイなので、最初は面喰ったのだが、読み始めたら最後、もう仕事をしてようが食事をしてようが、トイレに行こうが寝てようが、続きが気になって気になって仕方がないくらいの本だった。“米原さんの本の中で”という形容ではなく、“これまで読んだ全ての本の中で”一番面白かったと言っても過言ではないくらいだ。 |

|
世界わが心の旅 プラハ 4つの国の同級生 米原万里 (2)嘘つきアーニャの真っ赤な真実 : 米原万里 http://ima-ikiteiruhushigi.cocolog-nifty.com/gendaisekai/2005/02/post_4.html. |
|
米原万里「旅行者の朝食」という本に出ていた、トルコ蜜飴とハルヴァという外国製... 米原万里、そしてロシア [ 伊藤玄二郎 ] もっと泣いてよフラッパー 下旬の図書 米原万里さんの本でチェコ、ハンガリー、ルーマニア、ポーランドの東欧中欧は東洋... 心臓に毛が生えている理由 [ 米原万里 ] "ハルヴァ"を手に入れたいのですが・・・ 同時通訳士になりたい。対策を教えてください。 こんにちは。 私は通訳を目指して... 昶(姓名の名で 偏が永 旁が日)の読み方は? 【斎藤美奈子さん等マガジンレビューの有名人を他にも知りたいです。】 旅行者の朝食 よし!当たった |

長谷川ニイナ恋する季節 
愛人日記愛人日記 
19ESAT Daliy News Amsterdam July 19 2013 Ethiopia 
ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還PS2 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 攻城戦 
アニモーションANIMOTION - Obsession / アニモーション オブセッション 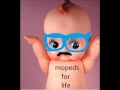
let's dancelets dance- David Bowie remix By " In Fiction" 
奇跡日川高校バスケットボール部 田中正幸 奇跡のシュート 
全豪オープンテニス全豪テニス準々決勝 ノバク・ジョコビッチvsベルディハ2013 1 22 |

[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
ケロミンTVに登場!
Higurashi Kai VN BGM - Hitoe (One Layer)
米原万里 ウェブ