
週刊文春1986年 国内2位
過激派”黒い牙”の幹部 筧が爆殺され、まきぞえをくって公安 倉木警部の妻が死亡する。筧の暗殺を狙っていた新谷は、現場から立ち去るものの、爆殺犯と間違えられ、騒動を怖れる依頼人 豊明興業から命を狙われることになる。死亡したかに見えた新谷だったが、記憶喪失の状態で生還していたのだった ・・・
何の予備知識もなく手にとってみたのだが、文句なく面白かった。キャラクターの造形がすばらしく、ストーリーの緊張感ある展開にぴったりあっている。特に倉木警部の冷徹さの中に見せる感情表現が良い。あっと驚く怒涛の結末。ミステリ好きには必読の書といってもいいだろう。公安警察シリーズというらしいんだが、本書を読了後、早速、残りの作品をAmazonに注文してしまったよ。
本書は、時制が前後するんで、とまどってしまうのだが、お終いまで、なかなか慣れなかったなぁ。
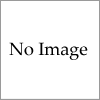
この作品における脚本、演出は乱暴に過ぎます。荒唐無稽な精神鑑定、考えられない大病院の杜撰なセキュリティ、実際にはあり得ない警察の捜査と捕り物、脳の障害についての説得力のない解説等など。この辺りがもっと丁寧に描かれていたら優れたサスペンスに仕上がっていたかもしれません。とはいえ、まったくの失敗作かというと、そうでもないのです。ラストまでなかなか
面白く観ることが出来ましたし、それなりに評価したいのです。ですから尚更、秀作にもなっただろうに惜しいなあ、と思ってしまうのです。

この作品における脚本、演出は乱暴に過ぎます。荒唐無稽な精神鑑定、考えられない大病院の杜撰なセキュリティ、実際にはあり得ない警察の捜査と捕り物、脳の障害についての説得力のない解説等など。この辺りがもっと丁寧に描かれていたら優れたサスペンスに仕上がっていたかもしれません。とはいえ、まったくの失敗作かというと、そうでもないのです。ラストまでなかなか
面白く観ることが出来ましたし、それなりに評価したいのです。ですから尚更、秀作にもなっただろうに惜しいなあ、と思ってしまうのです。

上巻では舞台が日本。PRマンが顧客である楽器会社の依頼、これもスペインのギター製作者の依頼なのだが、によりサントスということしか分かっていない人物を探すことから始まる。上巻は何か進行も遅く、ところどころにある少し間の抜けた冗談にも若干興ざめの感もあるのだが、下巻に入りスペインに舞台が移ってからは話しがフランコ総統暗殺になると話しが一気に展開し、テンポも早くなる。
そして最後に近づくにつれ話しがどんでん返しの連続となりがぜん面白くなってくる。最後に全ての面白さを取っておいたようなストーリーである。
著者自身のあとがきによると、この本はを書き上げたのは1977年6月。そのときまだ著者は作家となっておらず会社勤めの傍ら書き上げた。その後作家としてデビューし『百舌の叫ぶ夜』が売れ始めた頃、これを編集者に読んでもらって本になるに至ったと。
すなわちこれが著者の処女作なのである。
著者自身、稚拙な部分、気負い過ぎの部分があると述べているが、一方、またこうも述べている。
『処女作にはその作家のすべてが込められている、という。また、作家は処女作を越える作品は書けない、とも言う。ある意味で、それは正しいと思った。』
読者にも、著者の熱気が伝わってくる作である。

9年振りに出た岡坂神策シリーズの新作小説。
さすがベテランの技が光る読ませる小説でした。
現代調査研究所所長という私立探偵のような主人公・岡坂神策。
盟友である弁護士の桂本と食事をした後向かったバーで
神田小川町に新しく出来たタブラオ(フラメンコショーのあるレストラン)の宣伝ポスターを目にする。
スペイン通の岡坂は当然フラメンコにも精通しているが
桂本は全くのど素人にも関わらずポスターの写真を見て
気に入ったダンサー目当てに岡坂をなかば強引に誘い
タブラオ‘サンブラ’に繰り出す。
それが謎の事件の始まりだった。
店を出た二人は見知らぬカップルに尾行されている事に気付く。
彼らの尾行対象は岡坂なのか桂本なのかはたまた二人と意気投合した
バイラオーラ(フラメンコの踊り子)の神成真理亜たちなのか。
そして尾行の目的とは。
謎を追う内に岡坂は同じように事件を追う女性刑事・知恩炎華と知り合い捜査の協力に関わる。
しかし岡坂も知恩も化かし合い合戦で互いになかなか事件の尻尾を掴めない。
ギタリストや独文科教授なども現れ事態はどんどん複雑化を増して行く。
一番の巨悪は誰で一体どのような目的があったのか。
岡坂神策はバックストリート(裏町)の悪の罠の企みを看破できるのか。
かなり読み応えのある1冊です。
途中少し長丁場を感じますが終盤一気に読ませてくれる魅力があり
事件の真相が明らかとなった時
「そういう事だったのか!」と驚きます。
9年振りの新作はとても面白かったです。
次回作はせめて5年以内に出して欲しいところですね。
| 
