
北村太郎も田村隆一もそしてねじめ正一も、不勉強でよくわからない状態で手にとりました。
その時代、昭和初期に生まれ戦争に行き、そして戦後の時代を作った人たち。
彼らの中には今の時代に生きている我々より、情熱やあきらめやデカダンスや粘り強さが
ある。そして生きることに対する態度が違うと思うのだ。
これは詩人であり社会人であった北村だけが持っているものではなく、おそらくその時代の
色として皆が持っていたものだと思うのである。
53歳で妻以外に恋をして、でもその一途な情熱はこの小説からは熱くは伝わってこない。
また、妻に対してのおもいやりはなく、20年も一緒にいた年月は意味がないのだと思い
知らされる。「人の気持ちは変わっていくものだ」
その後に繰り広げられる北村の後半の人生は、詩というよりは、翻訳と生活が中心なものに
なっていく。
それでも彼は人生に淡々と立ち向かい、日々をすごしていく。
明子との出会い、阿子との出会い。全てがすばらしく、彼の生活を彩っていくが、でも淡々と
すごしていくのだ。
だがこの生活の中から彼は詩を生み出していく。
これが不思議なのだ。
詩人は詩人としての生活や思索があるわけではないのか?
我々とは違う生活や人生を通してあの詩が生まれるわけではないのか?
人生で与えられている時間は全ての人に平等である。
その中で何を生み出すかは全ての人に与えられた自由であり、彼らはたまたま詩であったの
だと。
作者の渾身の情熱が伝わるすばらしい作品。語り口もすばらしい。

にんべん三代目伊勢屋伊兵衛の苦境をはね返す努力と成功を描く半生記。
伊之助は大店の次男坊。
跡継ぎではない気安さの一方にある世の中ナナメに見る僻み根性とも
相俟って、なかなか商売に身がはいらない。
そんなところに父親が突然倒れ、兄と二人、いきなり双肩にのしかかる
重い店の経営。
当主を継いだ兄の婚礼に、客が来ないほど落魄した時代を乗り越えて、
にんべんは江戸一番の大店にのし上がる‥。
幼い頃の伊之助の疑問「商人は何のために商売を大きくするのか?」に、
父は「おまえもあきんどになるのなら、答は自分でみつけるのだな」と
応える。
立派に店を盛り返し、その答を見いだした時、伊之助は三代目伊兵衛を
継ぐ決意をする。
あきないとは?という重い命題に明快な回答をさりげなく示して、爽やかな
読後感につなげている。
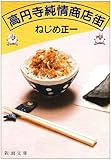
3部作だが、すべて気に入って何度も読んでいる。
60年代の商店街の様子が新鮮かつ懐かしく、それに触れたくてついつい手にとってしまう。
なにより主人公の少年にとても好感が持てる。
素直で子どもらしい部分も持ちながら、一人っ子として大人達に囲まれ、商売人の家に育った環境からか、世事に長けた判断もする点がリアル。
おそらく女性読者はこの少年にかなりの確率で非常に好感をもつと思う。
| 
