
おそろしくメロディラインの欠けたスコア。
あえてそれを狙っているのかもしれないが
これまでのジョン・ウィリアムスらしさが
あまり感じられなかった。

高機動型ジオン最こーーーーー

勘違いをしている人も多いようなので言っておきますが「宇宙戦争」というのは邦題であって、「全然戦争してねえじゃねえか!」、「スピルバーグの騙された!」というのは誤解な訳です。
そして、なにかと批判の多いラストですが、あれでよかったと思います。原作の小説通りだし。なんでもかんでも原作通りが良いということではありませんが、最初から最後まで、スピルバーグの演出はハンパじゃありません。ただ逃げ惑うことしかできない人々の様子。恐ろしすぎます。スピルバーグが描きたかったのはそれらのようなことで、ラストは無難に原作通りにしたのだろうとおもいます。
大体、原作のラストはもっと唐突で、もっとあっさりして、もっと、「ホントのこれでいいの?」なんていう書き方をしていたので、映画はそれよりも少しだけ娯楽性が高められていたと思いますよ。
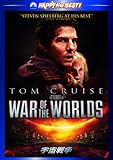
ストーリーは特にひねりはなく、原作小説を現代風にアレンジした映画化です。
SFというよりパニック映画として楽しむべき作品ですね。
何気ない日常の日々が、正体不明のメカによって地獄絵図と変わってしまう。
日常から非日常への変化という導入部が上手く、映画の世界に引き込まれていきます。
地下から現れた謎のメカは、殺人光線で攻撃してきます。
光線に当たると、人間は蒸発し灰になり、服だけがひらひらと舞い落ちるという、
一歩間違えはB級もののシーンを、見事に映像化しています。
最初の攻撃をなんとか生き延びた主人公と子供達が、
避難の旅の間に混乱し衝突しながらも、家族の絆を取り戻していきます。
主人公家族以外にも、大勢の避難民が登場しますが、みんなで協力するより、
我先に自分だけが助かればいいという人達ばかり。
パニック時ゆえ仕方ないとはいえ、主人公も例外ではありません。
生きる、生き残るということについて考えさせられます。
この映画で残念だったのは、主人公の娘がやたらキャーキャー叫びまくること。
叫び声が大きい=恐怖心が大きい、というのがハリウッド流なんでしょうか?
本当に恐ろしい時は声さえ出ないのでは?
この悲鳴のせいで、映画全体が安っぽく、嘘くさくなったように感じられてしまいました。

本作の成立や受容、評価については本書の訳者あとがきに言い尽くされていると思うので(東京創元社のHPで閲読可能)、「面白かった」以外に何か付け加えるのは難しい。あえて重複を恐れずにコメントすれば…
原題"The War of The Worlds"とは、地球という一つの世界の上での諸国間の戦いではない、地球と火星の戦いを意味しているわけだが、それでいて"The War of The Planets"でもないところがミソ。ある文明とそれとは全く異質の、しかしながら同格の次元にある文明との戦いであることを伝えている。
実際、多くのページが割かれているのが、火星人というヤツらがいかに我々人類とは違った存在か、にもかかわらずいかに進んだ文明を打ち建てているか、そして、生物として社会として優位にあるのは我々と火星人のどちらなのかについての科学色の強い記述であり、その記述も、例えば進化論や生態系の破壊、植民地主義等々地球上の実態と絡め実に説得力があって、つぶさに考証すれば疑問も出てくるのだろうが、筆運びのうまさがそれを感じさせない。お気に入りは以下のくだり。
「そして彼らの装具に関して、人間にとってなによりも驚くべきことは、人間の機械装置であればほぼ例外なく主要な特徴であるものが欠けているという興味深い事実である―つまり、『車輪』が欠けているのだ。(中略)火星人は車輪を知らなかった(これは信じがたい)か、車輪の使用を避けたばかりではなく、その機械装置に固定された旋回軸、あるいは比較的固定された旋回軸を使って円運動を平面上で直線運動に変える方法を不思議なことに採用していなかった。」(p.219。傍点を『』に変更。)
いかがだろうか?私見では、火星人文明の言いようもなく不気味な異質さが(これまた不気味な火星人の生態がつぶさに描写された後であるにもかかわらず)恐ろしくリアルに立ち上がってくる文章、三島由紀夫が『小説とは何か』で「たった一行のおかげで見事な小説となる」と語ったのは、こういう文章ではないかと思う。
つまり本作は優れて文明論的な地の文が面白いのであって(都市災害の描写の凄まじさや人間ドラマの迫力は言わずもがな)、数種ある映画版も有名なオーソン・ウェルズのラジオ・ドラマも原作の軒を借りただけ、それなりの面白さは別として、本作を読み終わった時に受ける感銘は希薄に終わっているのも無理はない(小説の映画化・ドラマ化は良かれ悪しかれ皆そんなものだが)。火星人が地球の細菌によって滅ぶ一見あっけない結末も、当時としては異端と言えるほどにヴィクトリアニズムから解放されたウェルズの、飽くまで人類進化史上の一事件(クロマニヨン人対ネアンデルタール人のような)として物語を描こうというクールな視点によるものだろう。
翻訳はいたって上質、丁寧。決定版と言っていい。これさえあれば、例えば読み易さ優先で訳を端折っていると思しき部分も散見されるハヤカワ版などは不要であろう。
それにしても、ホルスト『惑星』中の『火星』は確かにこの物語にぴったりのBGMだと思う。廃墟となったロンドンに平和が訪れる結末には『金星』。やがて主人公のモノローグが重なり、音楽とともに静かに終幕。暗転した後、再び回帰する『火星』に被ってエンディングのクレジット・ロール…という映画をいつも夢想する。
| 
