
屋根裏の二処女 (吉屋信子乙女小説コレクション)タイトルがすごいが、吉屋信子の作品には処女という言葉が何度も出てくる。無粋で乱暴な男に散らされていない、清らかで穢れなく、女性本来の女性、として私は素直に処女という言葉を納得してしまった。女学校卒業後、専門学校に通う「心に要を欠いた」章子はそれまでの寮を出てYWAに部屋を借りる。寮が満員とのことで、得られたのは青いペンキで塗られたにわか作りの屋根裏部屋であった。初めて自分の部屋を持った章子の満足と恍惚と寂しさが多くの形容でこってりと書かれる。そして、目的を欠いた毎日の中で、同じ寮の綺麗な異端者を恋うる思いが次第に募ってくる。二十三歳の「若書き」ではあるかもしれないが、技術で操作されていないぶん苦悩はリアル。「自分のしたいことが見つからないが、周囲に言われるまま学校に通っている」という人には時代を超えて響くところがあるだろう。そして、女性を押しのけて我先に電車に乗り込む男たちの姿が与える失望は、現代も同じ。 
花物語 上 (河出文庫 よ 9-1)
花物語は、大正5年(1916年)〜大正13年(1924年)に少女畫報に掲載された連作短編集で、 
わすれなぐさ (河出文庫)『わすれなぐさ』は凄くいい! 現代というぎすぎすした時代にうんざりしている乙女なら、絶対にこの本を読むべき。もう、一行読んだだけで、ロマンチシズムを追い求めし時にテレポーテーションできる! あと、本編もさることながら、嶽本野ばら氏による解説も幾何学的で美しいし、同じく氏による注釈も斬新で面白い。とにかく乙女万歳といった感じだぞ。 |

SkilletSkillet - "Sick Of It" Official Video 
克・亜樹ふたりエッチ LESSON.2 ~キス・キス・キス~ 
ザ・キング・オブ・ファイターズザ・キング・オブ・ファイターズ'94(ルガール使用) 
田中研二古川豪 公衆便所の伝説 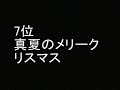
億万長者と結婚する方法「2000年テレビドラマ」 おすすめベスト ランキング 
佐藤秀峰【佐藤秀峰】「信用に値しない企業」フジテレビに絶縁宣言 
バルーンファイトバルーンファイト 
北村ひとみUSIC FES !! 2012 北村 瞳 |

[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
【ピース】夜なのにあさイチ~漢方スペシャル (12.02.25)
himalayan ninja goats
機動戦士Zガンダム メモリアルボックス (Blu-ray Disc) PV①
毬藻の唄 安藤まり子
西城秀樹 聖少女・ホップステップジャンプ++
吉屋信子 ウェブ
