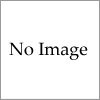
最初観たとき、単館上映だったので土曜日の銀座、もちろん人が沢山の映画館へ行ってみてきました。
…出てくるときに文字通り嗚咽を上げながら出てきました。 描写が繊細で美しい、失われゆく少年時代、純粋さの代償に手に入れるもの。 そんなものを伝えるの映画は吐いて捨てるほどあって、私は飽きもせずにそれらが大好きなんだけど、あきらかにこの映画はそれだけで「はい、オ・ワ・リ!ちゃんちゃん!」の領域を越えている。
美しさ、純粋さ、罪悪感、尊敬、憧憬…膨らませるだけ膨らませてこれは結論を提示しない。全部全部自分の中でつじつまを合わせねば行けない。 「ああ、あの主人公こう思ったんだ」という客観としてではなく、強く強く心に主観として残る感覚。この映画以外でこの感覚に陥ったことは無い。
もう二度と観ないかもしれません。好きすぎて。

何てことないシーンの連続なのに、ずぅっと惹きつけられつづける――
そんな力をもった画と音、独特なリズムの編集
とくに画について言うなら、とくに影・闇・黒だなぁ…
スペイン映画の十八番、やっぱりスゴイ
ケルトの末裔が棲むガリシア地方の1936年…
それだけでも、異国情緒を存分にかきたて、文字どおり夢見心地にさせてくれる☆
そして…あのED! この時空が置かれた歴史が顕わになる…
心に突き刺さるに決まってますよね
名作感ただよう名作♪
【覚書】
・ 本作は、宗教と深く結びついた「メロドラマ」っていう括りができる!貴重!
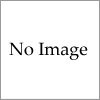
病弱であるため少し遅れて学校に行くことになった少年と心優しい先生との心温まる交流と戦争の暗い影を描いた作品。
子どもの頃、こういった先生に出会えた人はとっても幸せだと思います。こんな先生もいたなぁと昔をなつかしく思い出させる、お話です。 派手な演出や凝りに凝ったカメラワークなどがいっぱい使われている最近の映画にちょっとうんざりしている人にお勧めの映画です。
最初のほうのスペインの美しい映像で魅せる幸せな日々と、だんだん忍び寄ってくる戦争の影響の差があまりにも大きいので本当につらくなってきます。 ただの感動作品で終わらない、少し考えさせられる作品です。

観るたびにラストシーンには泣かされる。
老教師が黒板に蝶を描いて説明をするあたりで既に涙、涙。
痛烈なラストを知るだけに泣けてくる。
感動は人それぞれで、某映画サイトでは、秀逸と感じるラストの評価はわかれていた。
群集を前に連行される恩師に面と向い、少年が「アテオ(神を信じない人)!」、「アカ!」と叫び、
凍りつく恩師の目と合うシーン。拿捕された恩師を乗せて走り去るトラックを追いながら、
「ティロノリンコ!」、ついに「蝶の舌!」と叫び、さらに投石する痛烈なシーン。
投石は余計という声や、少年が泣きながら「蝶の舌」と言えば、もっと感動するのにと
残念がる向きもいたが、そうではないと思う。
少年が全く涙せず、表情すら変えず、つぶてを投げつけるように叫ぶからいいのだ。
安易なセンチメンタリズムを寄せつけない厳しさ。
ラストの少年の、無表情に近い硬い表情が杭を穿つように観る者の胸を打つ。

表題作「蝶の舌」は映像を言葉にしたような、土や緑の匂いを感じさせる作品。まだ政治や社会と対峙していない幼い少年が、初めて大人としての痛みを感じた瞬間を表したような短編でした。
派閥や迫害、そして戦争など現代では他人事のような感のある日本ではわかり辛い部分もありますが、子供の目から見た情景はストレートに響きます。 読み手に委ねられているのか、主人公の「僕」があえて物事に解釈をつけずにいるので、その時間を共有しているような感じが気に入りました。
| 
