
かつて熱烈に恋した人への手紙という形でストーリーが展開していく。恋の熱に浮かされた青年の心理描写が見事で、主人公の頼りない性格とあいまって、周りの人間からいじめられたり、からかわれたりする場面では読んでいてつらくなってくるほどだった。ここに記されたような青年期の恋の病は、若い頃に同じような経験がある人ならば大いに共感できると思う。実際に作者はオリンピックの代表選手として活躍したそうであるが、小説の主な舞台が洋上の船というところも、青春の象徴のような碧い海が若者たちを浮き立たせて、この小説の大きな魅力になっていると思う。時々熱烈な恋心と反転して現れる片思いの相手を汚く罵る逆説的表現が新鮮だった。
随分昔に書かれた作品(1940年 昭和15年)であるのだが、文章が生き生きとしていて、時にコミカルな箇所もあり、古臭い感じを受けない。一途で、不器用で、危うく、そして純粋な青春の恋。最後の一言がとても切ないが、これこそ青春の恋なのか。
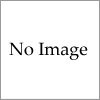
オリンピック選手でかつ作家から、好きでした好きでしたとラブレターをもらったら好きになるだろうか?それも、みんなに読まれることを承知のラブレターである。
勝手に好きになるのならまだ分かるが、このように告白されては困惑するだけであろう。
しかし、第三者が読めばこの片思いの恋は切なさを誘いついつい作者に肩入れしてしう。19歳の作者はもうめろめろである『どこが好きかときかれたら、ぼくは困るだろう。それほど、ぼくはあの人が好きだ。綺麗かときかれても、判らない、と答えるだろう』ともかく、彼女の総てが好きで好きでたまらないのだ。
それでいて、『ぼくはあのひとについて、なんにも知らないし、知ろうとも、知りたいとも思わない」とくる。
とにかく、一緒にいるだけで幸せなのだ。それというのも、オリンピック会場に向かう船に乗り合わせているため、いやおうなしに出会う機会は多い。作者は、それ以上のことは望んでいない。純愛というより、まさに片思いでしかない。
最後は、スタンバイミーの映画のように友人達のその後が紹介されて、作者が本当に聞きたかった言葉で終わっている。
切ない。作者がその答えを聞けたのか、おそらく聞かないまま、その思いを胸に秘めて自殺したのだろう。
| 